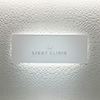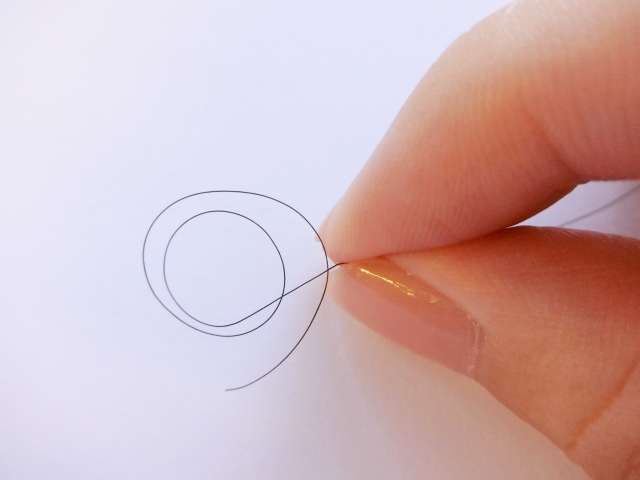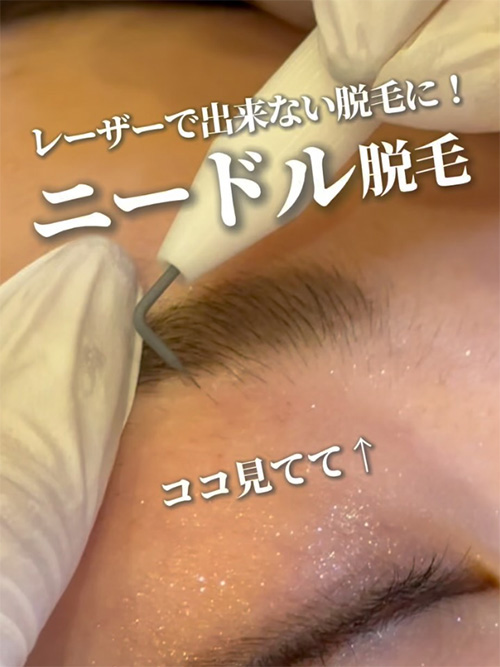LIGHT CLINIC 総合監修医
吹田 真一
国立循環器病研究センター勤務を経てLIGHT CLINICを開業。
医療脱毛を検討している方や、すでに施術を受けた方のなかには「医療機関での施術なら確定申告で医療費控除が受けられるのでは?」と期待する声が多く聞かれます。 実際に年間10万円を超える医療脱毛の費用は、家計にとって大きな負担となることも少なくありません。 もし医療費控除の対象となれば、所得税や住民税の負担が軽減され、実質的な費用を抑えることができるかもしれません。
しかし残念ながら、医療脱毛は原則として医療費控除の対象外となっています。 ただし「原則」という言葉が示すとおり、一定の条件を満たせば例外的に控除対象となるケースも存在します。 本記事では、医療脱毛と医療費控除の関係について、基本的な仕組みから具体的な申請方法まで、詳しく解説していきます。
確定申告の時期を前に、医療脱毛の費用を医療費控除として申請できるかどうか、正しい知識を身につけておきましょう。 特に治療目的での脱毛を検討している方や、すでに多額の医療費を支払っている方にとって、この記事が有益な情報源となることを願っています。
CONTENTS
医療費控除の基本と医療脱毛の位置づけ

医療費控除とは何か
医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計額が一定の基準を超えた場合に、確定申告を通じて所得控除を受けられる制度です。 この制度は、病気やけがの治療で経済的な負担が大きくなった納税者を支援することを目的としています。 具体的には、前年の1月1日から12月31日までの期間に支払った医療費のうち、10万円を超える部分が所得控除の対象となります。
医療費控除を受けることで、課税所得が減少し、結果として所得税と住民税の負担が軽くなります。 たとえば年収500万円の会社員が、年間30万円の医療費を支払った場合、20万円が控除対象となり、所得税率20%なら約4万円の税金が還付される計算になります。 この制度は、本人だけでなく生計を同じくする家族の医療費もまとめて申請できるため、世帯全体の医療費負担を軽減する重要な仕組みとなっています。
医療費控除の対象となる費用には、以下のようなものが含まれます:
• 病院での診察料、治療費、入院費
• 医師の処方箋にもとづく医薬品の購入費
• 治療に必要な医療器具の購入費
• 通院のための公共交通機関の交通費
• 歯科治療費(保険適用外の治療も含む)
• 妊娠・出産にかかる費用
• 介護保険サービスの自己負担分
ただし、健康保険組合からの給付金や生命保険からの入院給付金など、補填された金額は医療費から差し引く必要があります。 また、人間ドックや健康診断の費用は、異常が見つかって治療を開始した場合を除き、原則として控除対象外となります。 医療費控除を受けるためには、年末調整では対応できないため、必ず確定申告を行う必要があることも覚えておきましょう。
医療脱毛が原則対象外となる理由
医療脱毛は医療機関で医師や看護師が施術を行う医療行為であるにもかかわらず、なぜ医療費控除の対象外となるのでしょうか。 その最大の理由は、医療脱毛が「治療」ではなく「美容」を目的として行われることがほとんどだからです。 医療費控除の制度は、病気やけがの治療にかかる経済的負担を軽減することを目的としており、美容目的の施術は対象外と定められています。
国税庁の見解では、医療費控除の対象となる医療費は「診療又は治療の対価」と明確に規定されています。 つまり、身体の機能回復や疾病の治療を目的とした医療行為でなければ、たとえ医療機関で行われる施術であっても控除対象にはなりません。 医療脱毛の多くは、見た目を改善したい、むだ毛の処理を楽にしたいといった美容上の理由で行われるため、この要件を満たさないのです。
| 項目 | 治療目的の医療行為 | 美容目的の医療脱毛 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 疾病の治療・身体機能の回復 | 見た目の改善・利便性の向上 |
| 医療費控除 | 対象となる | 対象外 |
| 保険適用 | 多くが保険適用 | 自由診療(全額自己負担) |
| 医師の判断 | 医学的必要性あり | 患者の希望による |
さらに、医療脱毛が自由診療として扱われることも、医療費控除の対象外となる理由を裏付けています。 自由診療であること自体は控除対象外の直接的な理由ではありませんが、保険適用されない施術は一般的に治療の必要性が認められていないことを示しています。 このような背景から、医療脱毛を受けた場合でも、その費用を確定申告で医療費控除として申請することは原則としてできないのです。
美容目的と治療目的の線引き
医療脱毛における美容目的と治療目的の区別は、医療費控除の適用可否を左右する重要なポイントです。 この線引きは、施術を受ける動機や医学的な必要性の有無によって判断されます。 治療目的と認められるためには、脱毛を行わなければ日常生活に支障をきたす、または健康上の問題が生じるという医学的根拠が必要となります。
美容目的の医療脱毛とは、主に以下のような理由で行われるものを指します:
• 見た目を良くしたい、きれいになりたい
• 自己処理の手間を省きたい
• 肌をつるつるにしたい
• ファッションの選択肢を広げたい
• パートナーのために脱毛したい
• 周りの人と比べて毛深いのが気になる
一方、治療目的として認められる可能性があるのは、特定の疾患に対する治療の一環として脱毛が必要な場合です。 たとえば、わきがや多汗症の症状改善、アトピー性皮膚炎による肌トラブルの軽減、多毛症の治療などが該当します。 これらの場合、脱毛は症状を改善するための医学的な手段として位置づけられ、医師の診断と治療計画にもとづいて実施されます。
ただし、同じ部位の脱毛であっても、その目的によって扱いが異なることに注意が必要です。 たとえばわき脱毛の場合、単に見た目を良くしたいという理由なら美容目的ですが、わきが治療の一環として医師が必要と判断した場合は治療目的となります。 このような判断は患者個人ではなく、医師による診断と医学的見地からの判断が必要となるため、自己判断で治療目的だと主張しても認められません。
公的医療保険との違い

医療費控除と公的医療保険(健康保険)は、どちらも医療費の負担を軽減する制度ですが、その仕組みと適用範囲には大きな違いがあります。 この違いを理解することは、医療脱毛の費用負担を考えるうえで重要なポイントとなります。 特に「保険が効かない=医療費控除も受けられない」という誤解を持つ方が多いため、正確な知識を身につけておきましょう。
公的医療保険は、病気やけがの治療を受ける際に、医療費の一部(一般的に3割)を自己負担し、残りを保険が給付する制度です。 保険適用となる医療行為は厚生労働省が定める「診療報酬点数表」に記載されているものに限られ、これに含まれない自由診療は全額自己負担となります。 医療脱毛は美容目的の施術として自由診療に分類されるため、健康保険の適用対象外となっています。
一方、医療費控除は確定申告を通じて税金の還付を受ける制度であり、以下のような特徴があります:
• 保険適用外の自由診療でも、治療目的なら控除対象になる
• 年間の医療費が10万円を超える部分が対象
• 家族の医療費をまとめて申請できる
• 還付される金額は所得税率によって変動する
• 申請には確定申告が必要(年末調整では対応不可)
| 項目 | 公的医療保険 | 医療費控除 |
|---|---|---|
| 適用タイミング | 受診時に自動適用 | 確定申告で申請 |
| 対象範囲 | 保険診療のみ | 治療目的なら自由診療も可 |
| 負担軽減方法 | 医療費の7割を給付 | 税金の還付 |
| 美容目的の医療脱毛 | 適用外 | 適用外 |
重要なのは、保険適用外であっても医療費控除の対象となる治療があることです。 たとえば、歯列矯正や不妊治療の一部、先進医療など、保険適用外でも治療目的であれば医療費控除の対象となります。 逆に、保険適用される治療であっても、予防接種や健康診断のように治療目的でないものは医療費控除の対象外となる場合もあるため、それぞれの制度の趣旨を理解しておくことが大切です。
医療脱毛が医療費控除の対象になるケース

ワキガ治療に伴う脱毛
わきが(腋臭症)は、アポクリン腺から分泌される汗が皮膚の常在菌によって分解されることで、特有の強い臭いを発する疾患です。 この症状が重度の場合、日常生活や社会生活に支障をきたすことから、医学的な治療の対象となります。 わきが治療の一環として医療脱毛が行われる場合、その費用が医療費控除の対象となる可能性があります。
わき毛があることで、汗や皮脂が滞留しやすくなり、細菌の繁殖が促進されて臭いが強くなることがあります。 医療脱毛によってわき毛を除去すると、汗の蒸発が促進され、細菌の繁殖を抑制する効果が期待できます。 ただし、脱毛だけでアポクリン腺そのものを除去できるわけではないため、症状の程度によっては他の治療法との併用が必要となることもあります。
わきが治療として医療脱毛を受ける際の流れは以下のとおりです:
• まず皮膚科や形成外科で診察を受ける
• 医師による症状の診断と治療計画の立案
• 治療の一環として脱毛が必要と判断された場合に施術
• 診断書や治療計画書の発行を受ける
• 領収書とともに保管し、確定申告で申請
医療費控除の対象として認められるためには、医師の診断書が重要な役割を果たします。 単に「わきの臭いが気になるから脱毛したい」という自己判断では認められません。 医師が「腋臭症の治療のために脱毛が必要」と診断し、その旨を記載した診断書があってはじめて、治療目的の医療行為として認められるのです。
多汗症治療での脱毛
多汗症は、体温調節に必要な範囲を超えて過剰に発汗する疾患で、原発性多汗症と続発性多汗症に分類されます。 特にわきの多汗症(腋窩多汗症)の場合、医療脱毛が症状改善に効果的であることから、治療の選択肢のひとつとなっています。 この場合の医療脱毛は、美容目的ではなく治療目的として実施されるため、医療費控除の対象となる可能性があります。
多汗症の診断基準には、以下のような項目があります:
• 原因不明の過剰な局所性発汗が6か月以上続いている
• 日常生活に支障をきたすほどの発汗がある
• 週1回以上の頻度で過剰な発汗エピソードがある
• 左右対称に発汗する
• 睡眠中は発汗が止まる
• 25歳以下で発症している
• 家族歴がある
| 多汗症の重症度 | 症状の程度 | 医療脱毛の適応 |
|---|---|---|
| 軽度 | 発汗は気になるが日常生活に支障なし | 通常は適応外 |
| 中等度 | 日常生活に時々支障あり | 医師の判断による |
| 重度 | 日常生活に頻繁に支障あり | 適応となる可能性高い |
医療脱毛が多汗症治療として有効な理由は、毛がなくなることで皮膚表面の温度が下がりやすくなり、発汗量が減少するためです。 また、汗が毛に付着して滞留することがなくなるため、不快感や臭いの軽減にもつながります。 ただし、すべての多汗症患者に医療脱毛が適応となるわけではなく、症状の程度や部位、他の治療法との比較検討が必要となります。
アトピー性皮膚炎の治療目的
アトピー性皮膚炎は、かゆみを伴う慢性的な皮膚の炎症性疾患で、日本では人口の約10%が罹患しているといわれています。 この疾患の患者さんにとって、むだ毛の自己処理は皮膚への刺激となり、症状を悪化させる要因となることがあります。 そのため、医師の判断により医療脱毛が治療の一環として推奨される場合があり、この場合は医療費控除の対象となる可能性があります。
アトピー性皮膚炎の患者さんが自己処理で受ける肌への影響は深刻です。 カミソリによる物理的な刺激、除毛クリームに含まれる化学物質による刺激、毛抜きによる毛穴へのダメージなど、いずれも炎症を引き起こす原因となります。 医療脱毛によってこれらの自己処理が不要になれば、皮膚への刺激が大幅に減少し、症状の改善が期待できるのです。
アトピー性皮膚炎の治療として医療脱毛を検討する際のポイント:
• 皮膚科専門医による診察と症状の評価が必須
• 炎症が強い時期は施術を避ける必要がある
• レーザーの出力や照射方法を症状に応じて調整
• 施術後のケアを通常より入念に行う
• 定期的な経過観察と治療効果の評価
ただし、すべてのアトピー性皮膚炎患者に医療脱毛が適応となるわけではありません。 症状が安定していること、レーザー照射に耐えられる皮膚状態であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。 また、施術を行うクリニックもアトピー性皮膚炎への対応経験があるところを選ぶことが重要で、皮膚科と連携しているクリニックであればより安心して治療を受けられるでしょう。
医師の診断書が必要な理由

医療脱毛を医療費控除の対象として申請する際、医師の診断書は極めて重要な役割を果たします。 診断書は、その脱毛が単なる美容目的ではなく、医学的に必要な治療であることを証明する公的な書類となります。 税務署は、この診断書をもとに医療費控除の適否を判断するため、適切な診断書がなければ申請が認められない可能性が高くなります。
診断書に記載されるべき内容には、以下のような項目があります:
• 患者の氏名、生年月日、住所
• 診断名(わきが、多汗症、アトピー性皮膚炎など)
• 症状の程度と日常生活への影響
• 脱毛治療が必要な医学的理由
• 治療期間と施術回数の見込み
• 作成日と医師の署名、捺印
• 医療機関名と所在地
診断書の取得には、通常3,000円から5,000円程度の文書料がかかりますが、この費用も医療費控除の対象に含めることができます。 ただし、診断書は誰でも簡単に取得できるものではありません。 医師が診察を行い、実際に治療の必要性を認めた場合にのみ発行されるものであり、患者の希望だけで作成してもらえるものではないことを理解しておく必要があります。
| 診断書の要素 | 重要度 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 診断名の明記 | 必須 | 正式な病名が記載されているか |
| 治療の必要性 | 必須 | 脱毛が治療として必要な理由 |
| 医師の署名 | 必須 | 正式な署名と医師免許番号 |
| 医療機関の情報 | 必須 | 正式名称と所在地 |
さらに、診断書は確定申告時に提出する必要はありませんが、5年間の保管義務があります。 税務署から提出を求められた際にすぐに提示できるよう、領収書とともに大切に保管しておくことが重要です。 医師の診断書があることで、税務調査が入った場合でも、医療費控除の正当性を証明することができるため、安心して申請を行うことができるでしょう。
医療費控除の対象となる医療費・ならない医療費

控除対象になる医療費の具体例
医療費控除の対象となる医療費は、治療を目的とした幅広い費用が含まれます。 単に病院で支払った診療費だけでなく、治療に必要な医薬品の購入費や通院にかかる交通費なども対象となるため、正しく理解しておくことで控除額を最大限に活用できます。 ここでは、実際に医療費控除の対象となる具体的な費用について詳しく解説していきます。
診療・治療に関する費用として、以下のものが控除対象となります:
• 医師による診察料、治療費、手術費
• 入院費用(食事代を含む)
• 歯科治療費(金歯、セラミックなど保険外治療も含む)
• 不妊治療、人工授精の費用
• 視力回復のためのレーシック手術
• 鍼灸師、柔道整復師による施術費(治療目的)
• 医師の指示による按摩、マッサージ費用
医薬品や医療器具に関しては、医師の処方箋にもとづく医薬品はもちろん、市販薬でも治療目的であれば対象となります。 たとえば、風邪をひいて購入した市販の風邪薬、けがの治療のための絆創膏や包帯なども医療費控除の対象です。 また、治療に必要な松葉杖、補聴器、義手義足などの医療器具の購入費用も含まれます。
| 費用の種類 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 通院交通費 | 電車、バス、タクシー代 | タクシーは緊急時や歩行困難時のみ |
| 出産費用 | 分娩費、入院費、検診費 | 出産育児一時金を差し引く |
| 介護費用 | 介護サービス、おむつ代 | 医師の証明書が必要な場合あり |
| 歯科矯正 | 子供の歯列矯正 | 大人は治療目的の場合のみ |
特に注目すべきは、家族の医療費もまとめて申請できる点です。 生計を同じくする配偶者や親族のために支払った医療費も控除対象となるため、世帯全体の医療費を合算することで10万円の基準を超えやすくなります。 たとえば、単身赴任中の夫の医療費、別居している大学生の子供の医療費、同居している両親の医療費なども、生計が同一であれば合算して申請することができるのです。
控除対象にならない医療費の具体例
医療費控除の対象とならない費用を正確に把握することは、確定申告でのミスを防ぐために重要です。 医療機関で支払った費用であっても、治療目的でないものは控除対象外となります。 特に美容や健康増進を目的とした費用は、たとえ医師が関与していても原則として対象外となることを理解しておきましょう。
美容・審美目的の費用で控除対象外となるものには以下があります:
• 美容整形手術(二重まぶた、鼻の整形など)
• 美容目的の歯科治療(ホワイトニング、審美目的のセラミック)
• しみ、しわ取りなどの美容皮膚科治療
• 美容目的の医療脱毛
• 育毛、発毛治療(AGA治療など)
• 美容目的のボトックス注射
• 痩身目的の施術やサプリメント
健康維持や予防を目的とした費用も、基本的に控除対象外となります。 人間ドックや健康診断の費用は、その結果異常が見つかり、引き続き治療を受けた場合のみ対象となります。 予防接種、ビタミン剤などの健康補助食品、健康器具の購入費用も同様に対象外です。
日常生活に関連する費用で誤解されやすいものもあります。 メガネやコンタクトレンズの購入費用は、治療用の特殊なものを除いて対象外です。 自家用車での通院にかかるガソリン代や駐車場代も認められません。 また、入院時の差額ベッド代は、医師の指示や治療上の必要性がない限り対象外となります。
その他、以下のような費用も医療費控除の対象外となります:
• 医師への謝礼金
• 美容目的のサプリメント、健康食品
• 温泉療養のための旅行費用
• スポーツジムの会費
• マッサージ器の購入費用
• 親族への付き添い料
• 診断書の作成料(一部例外あり)
これらの費用を誤って医療費控除に含めてしまうと、税務調査で指摘を受ける可能性があります。 特に美容と治療の境界線があいまいな施術については、医師の診断書や領収書の但し書きを確認し、治療目的であることを明確にしておく必要があります。 不明な点がある場合は、事前に税務署に相談することをおすすめします。
年間10万円の基準について
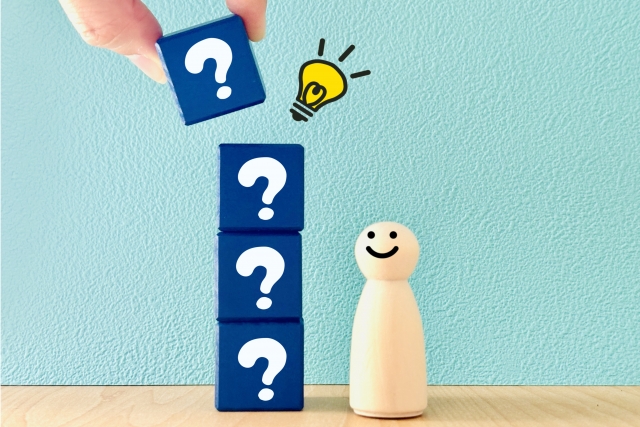
医療費控除を受けるためには、年間の医療費が一定額を超える必要があります。 この基準額は原則として10万円となっていますが、所得によって変動する場合があるため、正確に理解しておくことが重要です。 また、10万円という金額は思っているより達成しやすい基準であり、家族の医療費を合算することで多くの世帯が対象となる可能性があります。
医療費控除の対象額は、以下の計算式で求められます:
(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補填される金額)-(10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない額)
たとえば、年間の医療費が25万円、保険金で5万円が補填された場合、控除対象額は10万円(25万円-5万円-10万円)となります。 この10万円に所得税率を掛けた金額が、実際に還付される税金の目安となります。 所得税率が20%の方なら約2万円、住民税と合わせると約3万円の税金が軽減される計算です。
| 年間医療費 | 保険金補填 | 控除対象額 | 還付額(税率20%) |
|---|---|---|---|
| 15万円 | 0円 | 5万円 | 約1万円 |
| 30万円 | 5万円 | 15万円 | 約3万円 |
| 50万円 | 10万円 | 30万円 | 約6万円 |
10万円の基準は、実は多くの家庭で達成可能な金額です。 たとえば、家族4人で年間の医療費を考えると、定期的な通院で月3,000円×12か月=3万6,000円、歯科治療で3万円、子供の矯正治療で4万円といった具合に、すぐに10万円を超えることがあります。 特に出産、入院、手術などの大きな医療費が発生した年は、確実に医療費控除の対象となるでしょう。
なお、医療費控除の上限は200万円となっています。 つまり、年間の医療費から10万円を差し引いた金額が200万円を超える場合でも、控除対象額は200万円が限度となります。 ただし、実際に200万円の上限に達するケースは稀であり、ほとんどの方にとって十分な控除枠が用意されているといえるでしょう。
所得による控除額の違い
医療費控除の基準額は、総所得金額等が200万円未満の場合、10万円ではなく総所得金額等の5%となります。 この規定により、所得が少ない方でも医療費控除を受けやすくなっています。 たとえば、総所得金額等が150万円の方は、7万5,000円を超える医療費があれば控除対象となるため、より多くの方が制度を利用できるようになっています。
総所得金額等とは、給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引く前の金額を指します。 年収でいうと、おおむね年収310万円以下の方が総所得200万円未満に該当します。 パートタイマーや年金生活者、個人事業主の方などは、この優遇措置の対象となる可能性が高いでしょう。
所得による医療費控除の基準額の違い:
• 総所得金額等が200万円以上:10万円
• 総所得金額等が150万円:7万5,000円
• 総所得金額等が100万円:5万円
• 総所得金額等が60万円:3万円
また、実際の還付額は所得税率によって大きく変わります。 日本の所得税は累進課税制度を採用しているため、所得が高い人ほど税率が高くなります。 医療費控除による還付額は、控除対象額に所得税率を掛けた金額となるため、高所得者ほど還付額も大きくなる仕組みです。
たとえば、医療費控除額が20万円の場合、所得税率5%の方は1万円の還付ですが、所得税率23%の方は4万6,000円の還付となります。 さらに、住民税も一律10%軽減されるため、実際の税負担軽減額はより大きくなります。 このように、同じ医療費を支払っても、所得によって税制上のメリットに差が生じることを理解しておくことが大切です。
確定申告による医療費控除の申請方法

申告期間(2月16日〜3月15日)
医療費控除を受けるためには、確定申告期間内に申請を行う必要があります。 通常の確定申告期間は、毎年2月16日から3月15日までの1か月間と定められています。 この期間中に前年1月1日から12月31日までに支払った医療費について申告を行い、払いすぎた税金の還付を受けることができます。
ただし、医療費控除のみの還付申告の場合は、特別な取り扱いがあります。 還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 つまり、2024年分の医療費控除は、2025年1月1日から2029年12月31日まで申告可能ということです。
申告時期による違いと注意点:
• 2月16日〜3月15日:最も混雑するが、早めの還付が期待できる
• 1月中の申告:税務署が空いており、丁寧な対応を受けやすい
• 3月16日以降:期限後でも還付申告なら問題なし
• 過去分の申告:5年前まで遡って申告可能
• e-Taxなら24時間受付(メンテナンス時を除く)
| 申告方法 | 受付期間 | 還付までの期間 |
|---|---|---|
| 窓口・郵送(2〜3月) | 平日9時〜17時 | 1〜2か月 |
| 窓口・郵送(1月) | 平日9時〜17時 | 3週間〜1か月 |
| e-Tax | 24時間 | 2〜3週間 |
確定申告期間中は税務署が非常に混雑するため、時間に余裕を持って準備することが重要です。 特に3月に入ってからは駆け込み申告が増え、相談窓口も長時間待たされることがあります。 医療費控除のみの申告であれば、混雑を避けて1月中に申告するか、期限後に余裕を持って申告することをおすすめします。
必要書類の準備

必ず用意する書類一覧
医療費控除の確定申告を行うには、いくつかの必要書類を事前に準備しておく必要があります。 これらの書類は申告の基礎となるものであり、不備があると申告が受理されない可能性があります。 特に初めて確定申告を行う方は、早めに書類を揃えて内容を確認しておくことが大切です。
必ず用意すべき書類は以下のとおりです:
• 確定申告書(税務署やインターネットで入手可能)
• 医療費控除の明細書(国税庁ホームページからダウンロード)
• マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
• 源泉徴収票(給与所得者の場合)
• 医療費の領収書(提出は不要だが5年間保管義務)
• 保険金などの給付額がわかる書類
• 印鑑(認印で可)
医療費控除の明細書は、2017年分の確定申告から新しく導入された書類です。 以前は領収書の提出が必要でしたが、現在は明細書に医療費の内容を記載することで、領収書の提出が不要となりました。 ただし、領収書は自宅で5年間保管する義務があり、税務署から提出を求められた場合は応じる必要があります。
マイナンバーの確認書類については、マイナンバーカードを持っている方は1枚で本人確認が完了します。 マイナンバーカードを持っていない方は、通知カードや住民票(マイナンバー記載)に加えて、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類の写しが必要です。 e-Taxで申告する場合は、マイナンバーカードとICカードリーダーがあれば、書類の添付が省略できて便利です。
源泉徴収票は、会社員や公務員の方が年末調整後に勤務先から受け取る書類です。 医療費控除の申告には、この源泉徴収票の内容を確定申告書に転記する必要があります。 紛失した場合は、勤務先に再発行を依頼しましょう。
あると便利な書類
必須ではないものの、用意しておくと申告作業がスムーズに進む書類があります。 これらの書類は、医療費の集計や明細書の作成を効率化し、申告ミスを防ぐ役割も果たします。 特に医療費が多岐にわたる場合や、家族分をまとめて申告する場合は、これらの書類を活用することをおすすめします。
あると便利な書類と活用方法:
• 医療費通知(医療費のお知らせ)
• 交通費の記録(通院日と金額のメモ)
• 薬局のレシート(市販薬購入の記録)
• 医療費集計フォーム(国税庁提供のエクセルファイル)
• 前年の確定申告書の控え
• 還付金振込先の通帳
• 家族の医療費領収書
医療費通知は、健康保険組合や協会けんぽから年1〜2回送付される書類で、保険診療の受診記録がまとめて記載されています。 この書類を添付することで、記載されている分の医療費については明細書への記入を省略できます。 ただし、医療費通知に記載されていない自由診療分や、通知の対象期間外の医療費は別途明細書に記入が必要です。
| 書類の種類 | 入手方法 | 活用メリット |
|---|---|---|
| 医療費通知 | 健保組合から送付 | 明細書記入の簡略化 |
| 集計フォーム | 国税庁HPでダウンロード | 自動計算で集計ミス防止 |
| 交通費メモ | 自作または様式ダウンロード | 領収書のない経費の証明 |
交通費については、領収書がない場合でも申告できますが、日付、区間、金額を記録したメモを作成しておくことが重要です。 定期券の区間は除外する必要があるため、実際に支払った金額のみを集計します。 また、タクシーを利用した場合は、必ず領収書をもらい、利用理由(深夜、体調不良など)をメモしておくと良いでしょう。
確定申告書の作成方法

e-Taxでの申請
e-Taxは、インターネットを通じて確定申告ができる便利なシステムで、医療費控除の申告にも最適な方法です。 24時間いつでも申告でき、税務署に行く必要がないうえ、還付金の振込みも通常の申告より早いというメリットがあります。 初めての方でも、画面の指示に従って入力していけば、簡単に申告書を作成できる仕組みになっています。
e-Taxを利用するための準備として、以下の方法があります:
• マイナンバーカード方式(ICカードリーダーまたは対応スマートフォン使用)
• ID・パスワード方式(事前に税務署で発行を受ける)
• 確定申告書等作成コーナーから印刷して提出
マイナンバーカード方式は、最も推奨される方法です。 マイナンバーカードとICカードリーダー(3,000円程度)、またはマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンがあれば、すぐに始められます。 初回のみ利用者識別番号の取得や電子証明書の登録が必要ですが、2回目以降はよりスムーズに申告できます。
e-Taxでの医療費控除申告の流れは、まず国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスし、「作成開始」をクリックします。 次に提出方法で「e-Tax」を選択し、マイナンバーカードの認証を行います。 所得の種類で「給与所得」を選択し、源泉徴収票の内容を入力した後、所得控除の入力画面で「医療費控除」を選択します。
医療費の入力方法には、医療費通知を利用する方法と、明細を直接入力する方法があります。 システムが自動で10万円を超えているか計算してくれるため、計算ミスの心配もありません。 すべての入力が完了したら、内容を確認して送信ボタンを押すだけで申告が完了します。
税務署での申請
税務署の窓口で直接申告する方法は、職員に相談しながら申告書を作成できるため、初めての方や不安がある方におすすめです。 確定申告期間中は、多くの税務署で申告相談会場が設置され、職員や税理士が申告書の作成をサポートしてくれます。 ただし、混雑時は長時間待つこともあるため、時間に余裕を持って訪問することが大切です。
税務署での申告に持参すべきものは以下のとおりです:
• 必要書類一式(前述の必須書類)
• 筆記用具と計算機
• 認印
• 医療費の領収書(整理して持参)
• メモ用紙
税務署では、まず受付で「医療費控除の申告をしたい」と伝えます。 番号札を受け取り、順番が来たら相談コーナーで職員の指導を受けながら申告書を作成します。 医療費控除の明細書は事前に作成しておくとスムーズですが、会場で作成することも可能です。
| 時期 | 混雑状況 | 待ち時間の目安 |
|---|---|---|
| 2月前半 | 比較的空いている | 30分〜1時間 |
| 2月後半 | 混雑し始める | 1〜2時間 |
| 3月前半 | 非常に混雑 | 2〜3時間 |
| 3月15日付近 | 最も混雑 | 3時間以上 |
申告書の作成が完了したら、控えを必ず受け取ります。 この控えは、還付金の振込み確認や、翌年の申告の参考資料として重要な書類となります。 また、住宅ローンの申し込みや保育園の入園手続きなどで、確定申告書の控えを求められることもあるため、大切に保管しておきましょう。
郵送での申請
郵送による確定申告は、税務署に行く時間がない方や、遠方にお住まいの方にとって便利な方法です。 申告書と必要書類を封筒に入れて送るだけで手続きが完了するため、仕事で忙しい方でも無理なく申告できます。 ただし、記入漏れがあっても指摘を受けられないため、事前の確認が重要になります。
郵送での申告に必要な準備は以下のとおりです:
• 確定申告書(記入済み)
• 医療費控除の明細書(記入済み)
• 源泉徴収票(原本)
• 本人確認書類の写し
• 返信用封筒(控え返送希望の場合)
• 84円切手(返信用)
申告書類は、信書として郵送する必要があるため、普通郵便またはレターパックで送ります。 宅配便では送ることができないので注意が必要です。 消印の日付が提出日となるため、3月15日の消印まで有効ですが、余裕を持って発送することをおすすめします。
郵送時のチェックポイント:
• 申告書の記入漏れがないか再確認
• 押印箇所に漏れがないか確認
• 添付書類がすべて揃っているか
• 医療費の計算に誤りがないか
• マイナンバーの記載と本人確認書類の添付
• 管轄の税務署の住所が正しいか
返信用封筒を同封すると、収受印を押した申告書の控えを返送してもらえます。 この控えは、還付金の処理状況を確認する際や、翌年の申告の参考にする際に必要となるため、必ず返送を依頼しましょう。 また、書留やレターパックプラスを利用すれば、配達記録が残るため、より安心して送ることができます。
医療脱毛で確定申告する際の注意点

領収書の保管方法と期間
医療費控除の申告において、領収書の適切な保管は非常に重要な義務となっています。 2017年分から領収書の提出は不要となりましたが、5年間の保管義務は継続しており、税務署から提出を求められた場合は速やかに対応する必要があります。 特に医療脱毛のような高額な支出については、領収書の管理を徹底することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
領収書の保管で注意すべきポイント:
• 感熱紙の領収書は時間とともに印字が薄くなるためコピーを取る
• 年度ごとにファイルやクリアファイルで分類整理
• 医療機関別、家族別に仕分けしておく
• 領収書と一緒に診断書も保管
• デジタル化してバックアップを作成
• 交通費のメモも一緒に保管
領収書の整理方法としては、A4サイズのクリアファイルに月別・医療機関別に分けて保管する方法が効率的です。 各領収書には通し番号を付けて、エクセルなどで一覧表を作成しておくと、必要な時にすぐに探し出すことができます。 医療脱毛の領収書は、施術内容や回数が記載されているか確認し、不明な点があれば施術を受けたクリニックに確認しておきましょう。
| 保管書類 | 保管期間 | 保管のコツ |
|---|---|---|
| 医療費の領収書 | 5年間 | 年度別にファイリング |
| 医師の診断書 | 5年間 | 領収書と一緒に保管 |
| 確定申告書の控え | 7年間推奨 | 別ファイルで管理 |
| 医療費控除の明細書 | 5年間 | デジタルコピーも作成 |
万が一、税務調査で領収書の提出を求められた際に、紛失していたり提出できない場合は、医療費控除が認められない可能性があります。 さらに、虚偽の申告と判断された場合は、加算税や延滞税が課される可能性もあるため、領収書の管理は確実に行う必要があります。 5年間という長期保管になるため、引っ越しの際などに誤って処分しないよう、重要書類として管理することが大切です。
医療費控除明細書の記入ポイント
医療費控除の明細書は、申告の要となる重要な書類であり、正確な記入が求められます。 記入ミスがあると申告の修正が必要になったり、最悪の場合は控除が認められないこともあります。 特に医療脱毛のような高額な医療費を記載する際は、慎重に記入することが重要です。
医療費控除の明細書の記入で押さえるべきポイント:
• 医療を受けた人ごとに記載する(本人、配偶者、親族別)
• 病院・薬局ごとにまとめて記載することも可能
• 医療費の区分を正しく選択する
• 支払った医療費から保険金等で補填される金額を差し引く
• 医療費通知を添付する場合は該当欄にチェック
• 交通費は「その他の医療費」として記載
医療脱毛を記載する際は、「診療・治療」の区分を選択し、病院名と所在地を正確に記入します。 治療目的であることを明確にするため、「治療内容等」の欄に「多汗症治療」「わきが治療」など、具体的な治療目的を記載することが重要です。 単に「医療脱毛」とだけ記載すると、美容目的と判断される可能性があるため注意が必要です。
保険金等で補填される金額の記入も重要なポイントです。 生命保険からの給付金、健康保険からの高額療養費、出産育児一時金などは、該当する医療費から差し引く必要があります。 ただし、補填される金額がその医療費を上回る場合でも、他の医療費から差し引く必要はありません。
明細書の作成を効率化するため、国税庁が提供している「医療費集計フォーム」(エクセル形式)を活用することをおすすめします。 このフォームを使えば、自動計算機能により集計ミスを防げるうえ、確定申告書等作成コーナーにデータを読み込むことも可能です。 手書きで作成する場合は、計算ミスがないよう電卓で複数回確認することが大切です。
家族分をまとめて申請する場合
医療費控除は、生計を同じくする家族の医療費をまとめて申請できるため、世帯全体で10万円の基準を超えやすくなります。 この制度を活用することで、一人では控除対象にならない医療費も、家族分を合算することで控除を受けられる可能性があります。 ただし、誰が申告するかによって還付額が変わるため、最も有利な方法を選択することが重要です。
家族分をまとめて申請できる範囲:
• 配偶者(別居中でも生計が同一なら可)
• 子供(別居の大学生も生計同一なら可)
• 両親(同居または仕送りで生計同一)
• 兄弟姉妹(生計を同じくしている場合)
• その他の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)
申告者を決める際の重要なポイントは、最も所得税率が高い人が申告することです。 医療費控除による還付額は、控除額に所得税率を掛けて計算されるため、税率が高い人ほど還付額も大きくなります。 たとえば、夫の所得税率が20%、妻の所得税率が5%の場合、同じ20万円の医療費控除でも、夫が申告すれば4万円、妻が申告すれば1万円の還付となります。
| 年収(給与) | 所得税率 | 医療費控除20万円の還付額 |
|---|---|---|
| 300万円 | 5% | 約1万円 |
| 500万円 | 10% | 約2万円 |
| 700万円 | 20% | 約4万円 |
| 1,000万円 | 23% | 約4.6万円 |
家族の医療脱毛を含めて申告する場合は、治療目的であることの証明がより重要になります。 家族それぞれの診断書を用意し、各人の治療の必要性を明確にしておく必要があります。 また、支払者が誰であるかも重要で、実際に費用を負担した人が申告することが原則となっています。
還付金の計算方法
医療費控除による還付金の額を事前に把握しておくことで、申告の効果を理解し、モチベーションを持って手続きを進めることができます。 還付金の計算は複雑に思えるかもしれませんが、基本的な仕組みを理解すれば、おおよその金額を自分で計算することが可能です。 ここでは、具体的な計算例を交えながら、還付金の算出方法を解説します。
還付金を計算する基本的な流れ:
- 年間の医療費総額を集計
- 保険金等で補填された金額を差し引く
- 10万円(または総所得金額等の5%)を差し引く
- 医療費控除額を算出(上限200万円)
- 医療費控除額×所得税率=所得税の還付額
- 医療費控除額×10%=住民税の軽減額
具体的な計算例として、年収600万円の会社員が、年間35万円の医療費を支払い、保険金で5万円が補填されたケースを考えてみましょう。
医療費控除額の計算: 35万円(医療費)-5万円(保険金)-10万円=20万円
所得税の還付額(税率10%の場合): 20万円×10%=2万円
住民税の軽減額(一律10%): 20万円×10%=2万円
合計の税負担軽減額: 2万円+2万円=4万円
このように、医療費控除を申告することで、合計4万円の税負担が軽減される計算となります。 ただし、住民税の軽減は翌年度の住民税から差し引かれるため、還付金として戻ってくるのは所得税の2万円のみです。 住民税の軽減分は、翌年6月から1年間、毎月の給与から天引きされる住民税が安くなる形で恩恵を受けることになります。
医療脱毛が治療目的として認められた場合、その高額な費用が控除対象となれば、還付額も大きくなります。 たとえば、わきが治療として30万円の医療脱毛を受けた場合、他の医療費と合わせて申告することで、数万円の還付を受けられる可能性があります。 申告の手間を考えても、十分にメリットがある金額といえるでしょう。
よくある質問と回答
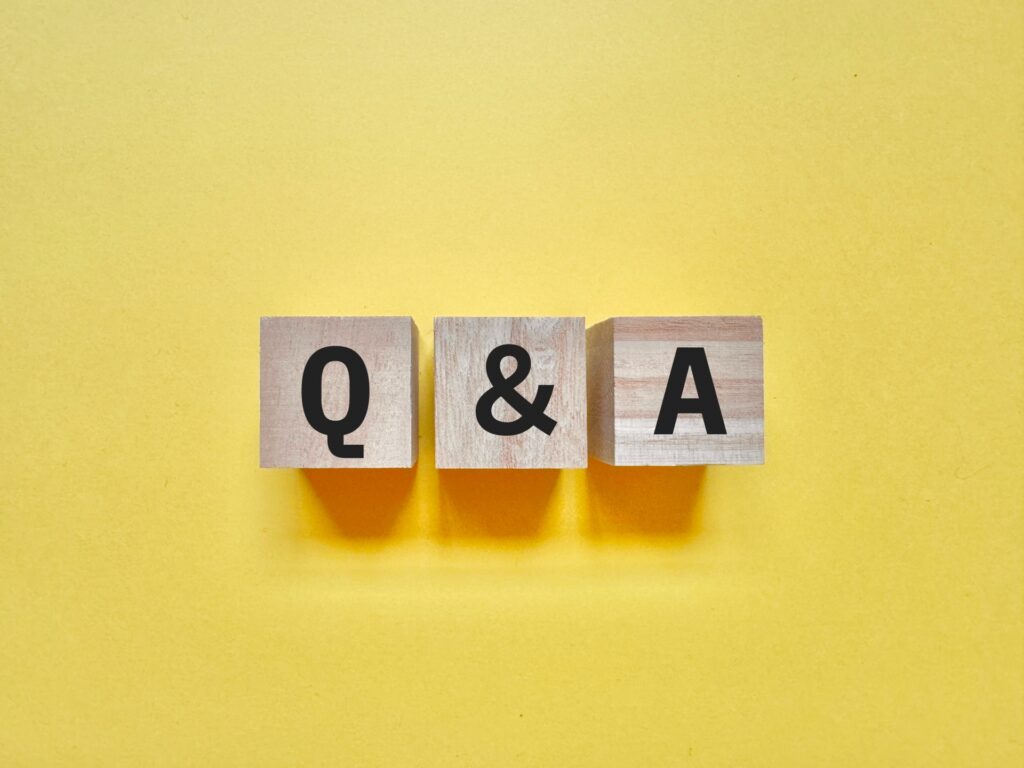
ヒゲ脱毛は対象になるか
男性のヒゲ脱毛についても、医療費控除の対象となるかどうかは多くの方が関心を持つポイントです。 結論から申し上げると、ヒゲ脱毛も原則として医療費控除の対象外となります。 その理由は、ヒゲ脱毛の多くが身だしなみや美容目的で行われるものであり、治療の必要性が認められないためです。
ヒゲ脱毛が医療費控除の対象外となる理由:
• 毎日のひげ剃りの手間を省く目的
• 清潔感のある見た目にしたい
• 肌をきれいに見せたい
• ビジネスシーンでの印象改善
• パートナーの希望による施術
ただし、例外的にヒゲ脱毛が医療費控除の対象となる可能性もあります。 たとえば、重度のカミソリ負けや毛嚢炎(もうのうえん)を繰り返し、医師が治療として脱毛を勧めた場合です。 この場合も、皮膚科での診断と治療計画にもとづいて行われる必要があり、美容クリニックで自己判断で受けた脱毛は対象外となります。
| 脱毛の種類 | 医療費控除 | 判断基準 |
|---|---|---|
| 美容目的のヒゲ脱毛 | 対象外 | 見た目の改善が主目的 |
| 皮膚疾患治療のヒゲ脱毛 | 対象の可能性あり | 医師の診断書が必要 |
| サロンでのヒゲ脱毛 | 対象外 | 医療行為ではない |
また、男性特有の疾患として、思春期から発症する多毛症がありますが、この治療としてヒゲ脱毛が行われる場合は医療費控除の対象となる可能性があります。 ただし、単に毛深いという理由だけでは多毛症とは診断されず、ホルモン異常などの医学的な原因が認められる必要があります。 気になる方は、まず内分泌科や皮膚科で相談することをおすすめします。
分割払いの場合の申告方法
医療脱毛は高額になることが多く、一括払いが難しいため分割払いを選択する方も少なくありません。 分割払いやローンを利用した場合の医療費控除の申告方法は、支払い方法によって異なるため、正しい理解が必要です。 ここでは、それぞれの支払い方法における申告のポイントを詳しく解説します。
分割払いの種類と申告方法:
• クレジットカード分割:契約時の全額を申告
• 医療ローン:契約時の全額を申告
• クリニック独自の分割:実際に支払った金額のみ申告
• デビットカード:支払い時の金額を申告
クレジットカードの分割払いや医療ローンを利用した場合は、実際の支払いが翌年以降にまたがっても、契約をした年の医療費として全額を申告できます。 これは、クレジットカード会社やローン会社が医療機関に一括で支払いを行い、患者はその後分割で返済するという仕組みのためです。 たとえば、12月に30万円の医療脱毛をクレジットカードの24回払いで契約した場合、その年の医療費として30万円全額を申告できます。
一方、クリニック独自の分割払い制度を利用した場合は、扱いが異なります。 この場合は、実際にクリニックに支払った金額のみが、その年の医療費控除の対象となります。 年をまたいで支払いが続く場合は、それぞれの年に支払った金額を、各年の確定申告で申告することになります。
申告時に必要となる書類も、支払い方法によって異なります。 クレジットカードやローンの場合は、クリニックが発行する領収書に加えて、ローン契約書やクレジットカードの利用明細書も保管しておくと安心です。 これらの書類は、支払い方法や金額を証明する重要な資料となるため、5年間は大切に保管しておきましょう。
医療ローンの利息の扱い
医療ローンを利用して医療脱毛を受けた場合、元本だけでなく利息も支払うことになります。 この利息部分が医療費控除の対象になるかどうかは、多くの方が疑問に思うポイントです。 残念ながら、医療ローンの利息は医療費控除の対象外となるため、申告時には注意が必要です。
医療ローンに関する医療費控除のルール:
• 元本(医療費本体):控除対象
• 利息・手数料:控除対象外
• 頭金:控除対象
• 保証料:控除対象外
• 事務手数料:控除対象外
たとえば、50万円の医療脱毛を金利5%の医療ローンで契約し、総支払額が55万円になった場合、医療費控除の対象となるのは元本の50万円のみです。 利息の5万円は医療費ではなく、金融サービスに対する対価とみなされるため、控除対象から除外されます。 この点を理解せずに総支払額で申告すると、後から修正を求められる可能性があります。
| ローン内容 | 金額 | 医療費控除 |
|---|---|---|
| 施術費用(元本) | 50万円 | 対象 |
| 利息 | 3万円 | 対象外 |
| 事務手数料 | 5,000円 | 対象外 |
| 申告可能額 | 50万円 | - |
医療ローンを検討する際は、利息が医療費控除の対象外であることを考慮して、総支払額を計算することが大切です。 金利が高いローンを選ぶと、実質的な負担が大きくなるため、できるだけ低金利のローンを選択するか、可能な範囲で頭金を多く支払って借入額を減らすことをおすすめします。 また、クリニックによってはゼロ金利キャンペーンを実施していることもあるため、そうした機会を活用するのも賢い選択といえるでしょう。
まとめ
医療脱毛と確定申告における医療費控除の関係について、詳しく解説してまいりました。 原則として美容目的の医療脱毛は医療費控除の対象外となりますが、わきがや多汗症、アトピー性皮膚炎などの治療目的で行われる場合は、例外的に控除対象となる可能性があることがわかりました。 重要なのは、医師の診断にもとづく治療の必要性があるかどうかという点です。
医療費控除を受けるためには、確定申告という手続きが必要になりますが、e-Taxを利用すれば自宅から簡単に申告できます。 年間の医療費が10万円を超える場合は、家族分をまとめて申告することで、数万円の税金が還付される可能性があります。 領収書は5年間の保管義務があるため、適切に管理することが大切です。
もし治療目的での医療脱毛を検討されている場合は、まず専門医の診察を受け、治療の必要性について相談することから始めましょう。 適切な診断書があれば、高額な医療脱毛費用も医療費控除の対象として認められる可能性があります。 この記事が、医療脱毛と確定申告について正しい知識を得る一助となれば幸いです。
LIGHT CLINIC 総合監修医
吹田 真一
国立循環器病研究センター勤務を経てLIGHT CLINICを開業。